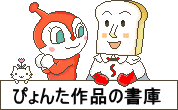
| 学生時代の作品をいくつか紹介します。 あえて手を加えずに、当時の文章のまま載せました。 著作権はぴょんたにあります。 無断引用・転載はおやめください。 |
十姉妹が卵を産んだ。 祖母から教えられたとおり、陽の当たる窓際へ朝一番に鳥籠を移してやると、やはり小松菜は菜差しからから抜け落ちていた。前夜も、一心についばむ音が遅くまで部屋じゅうに響いていたので、落ちて糞をかぶっているのは、根元のかたい部分だけだ。それで、新しい小松菜を差してやろうとしたのだが、二羽の十姉妹はともに壷巣から飛び出し、籠の中をやたらと羽ばたきまわって仕方ない。牡蛎粉(ぼれいこ)や羽毛があたりに散るだけだ。そのとき、壷巣の奥に白い卵がひとつ転がっているのが見えたのだ。 小指の爪ほどの卵である。よく見ると、殻はうっすらと桃色がかっていた。 ちょうど、番いがなかなか卵を産まないことを気にかけて、祖母が小鳥屋へ通いつめたりもして熱をだした矢先である。 二羽の十姉妹は新鮮な小松菜をつつき、粟や稗や牡蛎粉に夢中になり、交互に水浴びをしては滴を飛ばす。ともに黒いぶち同士の番いである。高い声でさえずるほうが雄で、雌は低く喉を鳴らすのだと祖母は教えてくれたのだが、わたしにはまだ聞き分けられない。ただ、一羽がさかんに小松菜をついばみ、桃色だったくちばしの端が緑に染まるほどなので、こちらが母鳥なのだろうかとも思う。 昼すぎに、爪切りと柘植の櫛を届けに行った。 ベッドが六台も入っているというのに、咳ひとつ聞こえずいやにしんとした病室ある。 祖母はいちばん窓際のベッドで眠っていた。頭まですっぽりと布団をかぶり、枕に広がるわずかな白髪がちらりとのぞいているだけである。その掛布団に、陽が深く差しこんでいた。 脇の丸椅子に腰を下ろすと、窓からは、枯れすすきの野原が一面に見下ろせた。長く伸びた穂や鋭い葉も、今では黄金色に色づいている。その上、おだやかにそよいでいるかと思うと、突然、その綿穂が一斉に吹きあげられて渦巻いたりもした。中には、うまく風に乗って、この窓辺まで届かんばかりのものまであった。 面会時間を過ぎても祖母はいっこうに目を覚まさないので、また出直してくることにした。枕元の棚に、爪切りと櫛の包みをそっと置く。般若心経の隣である。 ベッド全体が夕日を浴びて、まぶしいくらいだった。フックにかけておいたコートも心地よく温まっていた。 そのとき、一段と強い木枯らしが窓越しにも高く鳴った。さらに、小鳥の甲高いざわめきも混じり合う。 すすきは強風にあおられて大きく振れている。そして、その枯草にしがみついてともに振られているのは雀である。目を凝らすと、野原のあちらこちらでも同じように雀が揺れている。かなりの群れのようだ。その一羽一羽が、羽をばたばたさせながらも、決して振り落とされもしない。舞いあがる綿毛で、野は一見すると朝靄がたちこめたようでもある。 その晩のうちに風はぴたりとやんだ。 日に日に朝の鳥籠が冷えていくのがわかる。殊にその朝は冷たく、十姉妹は壷巣の奥でぴたりと身を寄せあっていた。それでも、朝日を浴びるとさっそく顔を出し、止まり木から止まり木へと飛びまわってさかんに鳴きはじめた。珍しく、小松菜がほとんどそのまま残っていた。その側を、二羽は短く鳴いてまわる。強い声で、途切れたような、妙な鳴きかたである。 卵がひとつ、籠の隅に転がっていた。殻がへこみ、鮮やかな黄色の中身が流れ出している。壷巣の中を覗きこんでみると、こちらでも殻にひびが入り、その隙間から黄身が垂れかけていた。 鳥籠に手を突っ込んで巣ごと取り外すあいだも、二羽はやはり激しく飛びまわって鳴いた。 手に余るほどの壷巣を、ゆっくりと傾ける。綿毛のような羽根や、小松菜のしなびた切れ端、干からびた緑の糞と一緒になって、卵は転がり出てきた。 巣のいちばん奥底には、白い細糸が幾重にも敷きつめられていた。それだけを残して空にしたものを、元の場所にまたくくりつけてやった。それでも十姉妹は、二本の止まり木の間を落ちつきなく羽ばたきながら、鋭く鳴きつづけている。 ひび入った卵を、そっと掌にのせる。殻についたわずかの黄身は、すでに乾きかけていた。光にかざしてみると、一直線に貫いている亀裂の筋が黄色く透きとおっている。 指で触れてみると、そこからふたつに割れた。掌にさらりと広がった液体は、温かくもなく、冷たくもなく、ただにおいが立つ。 やはり日ごとにひやりとしてくるガラス窓を開ける。また風が吹きはじめていた。思いのほか強い北からの風で、白い羽毛や糞のかたまり、小松菜のかけら、手の上の破片までもが、あっという間に吹き飛んだ。殻だけは風に乗れずにすぐに落ちていったが、それもやがて見失ってしまった。一面に降りた霜で、野芥子の鋭いロゼットさえ見つけられない朝のことである。 |
その場所からはなにが見える? 学校への石階段を八十四段までのぼったところで ともだちが提案した 「同窓会を開こう」 両側からハコネウツギの繁りが突き出していてピンクの花がちらちら揺れている そのせいで川向こうの教会も見えない けれども思い出すとつたの這う具合まではっきりしている 美術の時間に描いたことがある さえぎるもののない屋上からだ あのカンバスの十字架は破かれ焼かれてしまったが ともだちは鞄の中をごそごそやって 同窓会賛成派の九十六人の署名がびっしりの紙切れをわたしにつきつけた 名刺くらいの小さな、薄っぺらい紙切れ ともだちは距離感がわからないやつだから 紙がわたしの胸につよく当たって痛かった 変な痛みがぶりかえす 皮膚という皮膚がぜんぶ一斉にひび切れてケロイドになったような 痛みは脈とともに強くなる 喉はからからでちっとも動かない 汗が背中でひんやりして ともだちはニコニコしながら末尾にわたしの名前を書きこんでくれた 途中で鉛筆の芯が四回も折れ わたしの名はいちばん汚く、いちばん小さく、はしっこだった 「ああ、そういえば」 ともだちの声はすらすらとなめらか 「そういえば、いつもそうだったよね」 ともだちにとってはふと思い出した懐かしいできごとなのだそうだ わたしは渾身の力でともだちの胸ぐらをつかみあげていた 視界がちょっと高くなると途端にやってくる怯えの情けなさ しかしわたしはともだちを罵る言葉を思いつけなかった こんなときに限ってなにひとつとして浮かんではこないではないか あのようにことばで責めるのはきっと心地よいものだろうに ともだちはまだ怖がっている その場所からはなにが見える? ざまあ見やがれである 紙切れをともだちの胸ポケットから奪い取る すがすがしい 勝ち誇って ともだちのへんてこりんな名前だけを鉛筆でぐちゃぐちゃに消してやった 4Bの芯はあっという間にすりへった 雨だれ 傘を持ってこなかった 予報では東京全域90%と言っていたのに 新大久保に着くともうどしゃぶりだった はげしい降りで ビルがいっせいにかすみ どれも全部ねずみ色で同じになる 彼は15分も遅れてきたけれど 傘はさしていた 紫色のビニール傘 肩をつかまれて 「一緒に入るだろ?」 たしかに、わたしひとりだけびしょびしょになるのも気持ちわるいよね でもわたしと彼が傘の中でぴったりくっついているのに比べたら? どこかで買ってきたたいやきを電子レンジで温めなおす 甘いお菓子を用意してくるのにも、今では口をはさまないでいられるようになった 甘い匂いにも我慢できるようになった 甘い唾液にも、ことばにまでも もちろん、わたしと彼とがぴったりくっついていることにも 窓に当たる音がするほどの大雨 すこしだけ窓を開けてみる 中から見てもやっぱり同じ どの看板も建物も似ているし どの窓から眺めても大粒の雨だれ どんどん激しくなったあとは ぱったりとやんでしまえば 荷車 最悪の乗り心地の荷車で わたしは膝をかかえている 狭い空間にちぢこまって 飛び出してしまわないように強く 夜はまだ明けない 荷車は枯草の葉や根で編まれているので 手をかけただけでするするとほつれ ちぎれた葉は後方へ飛び去った 猛スピードでわたしを運びゆき 赤錆をまき散らし 4つの車輪は今にも外れて転がり脱線しそうで 荷車が飛び跳ねるたびに その中でわたしも一緒に飛び跳ねる 生きていない植物も狂暴である 顔を上げると びゅんと音を立てて頬をかすっていく 一瞬のことなのでこの手につかむこともできず わたしを乗せていることなど知るよしもない荷車で レールは闇の奥へと 季節 昨日から荷物を持ちすぎていた 彼女のために働きすぎていた それでもまだまだ残っている 次はタンス、次はドレッサー、そのあとは本棚、それからMDコンポも 汗を畳に滴らせないように わたしは1メートル運んでは荷を下ろし 流れる汗をこまめに拭わなければならない 彼女はといえば いち早くソファの荷をほどいて横たわり なつかしい写真を見つけだしては語っている わたしの知らない地をだ 頭の中まで湿気でぼんやりじっとり曇っている 今わたしが運ばなければならないのはNECのばかでかいパソコンで 持ち上げると背骨からちいさな音がするが彼女には聞こえやしないだろう 彼女はメールを12人とやり取りしていると自慢げである 「ちょっとは嫉妬するでしょう?」 彼女は笑うとき一本の歯も見せない 「全然」と答えてやると彼女はまた笑う 気味のわるい笑いかたなのだが 「嫉妬する?」 いつだってそう それでわたしはまた嘘つきということにされてしまった 罪名は今のところ3つ 不潔、能天気、そして嘘つき 的を射ているので仕方がない 隣の部屋から男女の声が聞こえてくる 「最高気温が33度なんだぜ?」 「しょうがないでしょ?」 「まだ夏じゃねえのになあ」 「でも、もう梅雨じゃないでしょ?」 「見ろよ、すげえ雲」 「知らないの? 積乱雲っていうのよ。ばかね」 「飽きずに日焼け止め塗りたくってる奴に言われたかねえよ」 さしのべる手 「ここのプラットホームは実に急傾斜です。 ですから、もし、万が一、何かの間違いでわたしが足を滑らせたとしても、 わたしを助けてやろうなんて決して思っちゃいけませんよ。この傾斜で引っ張り上げることなんて、できやしませんからね。 よろしいですか。 あなたが手をさしのべてくれても、わたしはそれをふり払うでしょう。わたしは、生きるべきときは自分の力だけで生き延びたいのです。わたしは絶対につかまったりはいたしませんよ。たとえあなたの手がどんなにつるつるで張りがありセクシーでなまめかしくとも。 いいえ、プラットホームをご覧なさい。つるつるに磨かれていますね。あなたが足を滑らせてしまったときは、わたしはあなたをつかみます。手だろうが足だろうが、一本の髪の毛だろうが、わたしは絶対につかんで引っ張ります。 わたしはあなたが好きですからね。 でも、あなたはわたしなんて愛してもいないくせにねえ?」 あしたも夜がくる 窓から身をのり出すと はるか下の地面には雪が積もっている いつのまに降ったのだろうか わたしと鎖でつながれたクローン実験体の新入りはわざわざ教えてくれた 今までずっと降ってたじゃないかよ。しんしんと降ってたじゃないかよ。いったい何を見てきたんだ? ほんとうは互いに遠くにいるのが摂理なのだから 体を触れあっているとたちまち吐き気がもよおしてくる いま、何十メートルも下の新雪に向けて わたしは胃の中のものをひゅるりと吐きおとす 逆流するゲロのせいで食道がひりひりする 当然である 昨日今日で32回もそうしているのだから わたしが吐くと実験体も同じものを同じようにして吐く 実験体にはこれがまだ7回目の吐瀉だ 若くてうらやましい やはり実験体もわたしと触れあっているのがいやなのだろう わたしが吐けば実験体も吐く 交代でげろげろやっていると まるで会話しているかのようでおかしい マジックミラーの向こうの白衣の研究員にも、 わたしたちが上機嫌でおしゃべりしているように見えるかもしれない そして研究員は第7483号の成功を所長に報告し 所長は満足そうに二度も三度もうなずいて第7483号実験体の存続を告げる 今回もうまくいきそうである 夜がくればわたしたちは体を寄せあってひとつのベッドで寝る まどろんでいても ふたりの間の鎖がじゃらじゃら音を立て たいていの新入りはなかなか眠れないが 第7483号実験体は眠りにつくのがわたしよりちょっとだけ早いようだ 実験体の心臓がゆっくりになってから わたしは我慢できずに枕に吐いた 実験体も眠ったまま一緒に吐いた わたしたちは一日のうちでこの時間帯がいちばん仲よしである 24時間体制の研究員はすべてをちゃんと記録してくれている 実験体の体を抱きしめる夜もあることまで 朝がくれば 新しい次の実験体とわたしは やっぱり何かの会話をしては吐いて、吐いて そうしてわたしはやっと一日分の歳をとり また夜がくれば どうしようもなく わたしは実験体を抱いて眠る 前の実験体のことはその頃にはもう憶えていない 火事だ! 「火事だ!」 走り出てくる男が叫んでいる 「納屋が燃えているぞ!」 家族全員がおどろいて起きだし 「バケツを持ってこい、ありったけだ!」 父はパジャマのまま炎のあがる藁に踏み込んでゆく 「裸足ではやけどしてしまうわよ!」 母が戸口からゴム草履を投げ込む 「ありがとう!」 奥から父が、おそらく笑顔で答えている 妹は消防隊を呼びに駆け出した はおったコートの裾がひらひら揺れて 逃げるように一目散 戻ってくるころには全焼だろう 「だめだった。豚も全滅だあ。だめだった」 父は涙を流している その右手には黒焦げの豚の尻尾 くるりと巻いている 「うむ、上質の接着剤ができる、しかも大量にだ!」 からくり屋敷で研究をしている若い学者がうしろに立っていた 「こんな好条件はなかなか揃わない。君には気の毒だけど、ぼくは今すごく興奮している。 第八ぜんまい試作品が、これでうまくいくかもしれない」 乾燥藁束……700キログラム 雄豚(種豚)……6頭 雄豚(食用)……5頭 雌豚(妊娠中)……4頭 雌豚(食用)……8頭 子豚……10頭 安価な飼料……100キログラム 木製農具……数点 木造藁葺き平屋、築22年 以上を2000℃以上の高温で40分前後加熱する。刺激臭発生→対策は? と、彼は手帳に書き込んだ 「そうと決まったらあとは待つだけだ」 冷却は急速でなくとも可(余熱で熟成が進み、 より高い粘接着効果が得られるはずである=コール真性昇華の法則・第四項) それで彼は手帳をポケットにしまった 「それにしてもすごい黒煙だなあ!」 わたしはしくしく泣いた 涙を指で拭ってくれた彼も涙ぐんでいた 火の粉を巻きあげて藁葺き屋根が焼け落ち 彼の指のドライバーだこはオレンジ色に照った よい日 自動改札の扉は閉じた 目の前で音をたててばしんと 行く手をふさいでいるのはエレベーターの分厚い自動扉 「開」のボタンを何度つよく押してもだめ 悪びれもしない 電気が通じていないにちがいない むりやりこじ開けようとしてもびくともしないのでホームに戻ることにした 仕方なく戻ったのである ホームなら人がたくさん行き交って教室より楽しいし 夜になったらお父さんが帰ってくるのだから そのときに一緒に出ればいいだけのことなのだ 改札の向こうでわたしの様子をうかがっていたともだちは顔を見せなくなった 三回目に楽しそうに笑ったのが最後 飽きられた? 結構なことでしょう ともだちが思っているほどわたしは弱虫ではない ということを今日はともだちに知らしめることができたよい日であるし 明日からはわたしを見直すだろう ともだちはほんとうは気が弱かったりして もしかしたらレスキュー隊を引き連れてくるかもしれない 下りホームの木のベンチにぺったり座って 万に一つを想定するなんてばかばかしいけれど 担架を抱えたレスキュー隊員にわたしは礼を言う? そしてともだちにも? そしてレスキュー隊員もともだちに礼を? なんということか! もう日も落ちるころ 最終電車はまるで新幹線そっくりのさわやかさ 修学旅行生ばかりがすらすら降りてくる けれどお父さんの姿がない 電車に近寄る 白線の外側に足を踏み入れてしまったのか ホームと電車のすきまにわたしは落ちた するりと、吸い込まれるように 暗い空間にかすり傷ひとつなくうつ伏し 背中を反らして見上げると 古びた蛍光灯が黄に輝き毒々しく 発車ベルの振動が下腹に伝わり ともだちの顔が見え 足首をひかれてわたしはそうして死んだ 恋人 わたしたちは交代で漕いだ 20分待ちでやっと回ってきたスワン号だ 緑色の古い貸しボート けれど塗料はほとんど剥げてしまって 苔が生えただけのように見える 漕ぐのはわたしのほうがうまい 彼は手首を使おうとするからだめなのだ わたしが櫂を握っているあいだは 退屈そうに始終きょろきょろしている 湖面も緑色だ 岸ちかくはきれいに透き通っていたけれど 深いところへ来ると 苔色以外の何色でもない その青くさい色が濃くなっていくにつれて わたしたちは黙りこくるようになっていった 話をしないでいると もっと聞こえてくる 櫂がつくる新たなさざなみが 漕ぐたびにどんどん大きくなって 時には彼がボートの中に寝そべって わたしの足に口づけることもあった わたしたちは一緒に寝そべって 長い間そうしていたこともあった まったく、波が聞こえなくなることだってあったのだ 時間が迫ってきていた 櫂に伸ばしかけた手を 彼も止めはしない けれど わたしたちはその瞬間を同時に見た 淀んだ濃緑の淵に 魚の腹がてらりと光ったのだ 三刻三景 午前5時 浅い水路を発泡スチロールの箱がくだってゆく ゆっくりと、たまに向きを変えたりしながら 岸辺に、せり出した小さな平屋と大きな柳 葉先は水面にぺったり浸っている 窓際の物干し竿には 半ズボンと紅白帽子 白く濁ったしずくがぽたぽた落ちて 淀みに溶けてくだってゆく 午後11時 暗い水路にタワーの灯りが黄色くうつっている 柳がそよげばにじんで消え、そしてまた輝きだし せり出した暗い窓への反射もみずみずしく しかし物干し竿の衣服はひからびている 紅白帽子の伸びきったゴムは揺れもせず からからに乾いているような *** くずはのもり公園には 昼どきになると木陰が多くなる それで涼しいものだから 母娘が弁当を食べに来る お母さんがシートを広げるあいだ 女の子は花を摘んであちこち走り 昼顔をつるごと引っ張りしりもちをつく 咲いたばかりで薄紅色である アリの行列は見向きもしない よけて通るところをみるとウインナーは嫌いなのか それで女の子は麦茶の河を氾濫させた 溺れながらやっとウインナーにしがみつくアリを 女の子はかならず助ける ぬかりなく、紫陽花の葉の方舟を用意しているのだ よく見ると アリは白い卵を運んでいるではないか 救われたアリの方舟を両の手に 女の子は母親へ走り寄り そのとき1匹が落ちた 母親の膝で はたかれたアリはぽんと跳んだ 小さな卵をしっかりくわえたまま *** 最終電車では2人分の席しか空いていなかった 腹を抱えた妻を先に座らせる 夫はそれから隣に腰をかけ おむつで膨れた長男を空いたすきまにねじりこむ 妻はさっそく寝息をたてて 息子は流星を探して叫びつづける 夫が読み進めているのは三国志である 電車は郊外へ向かう ときどき、膨れた腹をなでさすり 動かない妻を見る それから長男に言い聞かせることもする 「おまえの名前の由来はな」 得意げに 幾度めなのか 「かんうって誰だっけ?」 実に大きな長男のあくびである |
核戦争を夢見る美容師 1丁目の灰色の建物の2階にあるヘアーサロン・ヤングで 半年と24日前に髪を洗ってくれた背の高くて細いお兄さんは きのうは髪を切ってくれるまでに昇進してた 12月には茶髪ストレートの坊ちゃん頭だったけど きのうは真っ赤なツンツン頭になっていた ずり落ちそうな太いズボンの腰についてるホルスターみたいな黒革のケースの中には 四種類の櫛と四種類のはさみが入ってるんだとか 濡れた髪をとかしてもらいながら 小説を書いていると言ったら お兄さんは 「僕も書いてるんですよ」って話しはじめてしまった 洗髪してると 耳に穴がふたつあるお客さんがいて そこからくさい空気を出すんだってさ 新人類と旧人類の世界大戦なんだって ラストの一文までもう決まってるって お兄さんは私の髪の毛をどんどん切りながら得意げに自慢した 「核爆弾のスイッチが押された」で終わるんだ あんまりおもしろくないと思ったけど 言わないで笑っておいた ペンネームはコウダサルヨシっていうんだって教えてくれた 将来の大ベストセラーSF作家に髪を切ってもらえるなんて幸せですよ だってさ 半年と24日前に頭を洗ってもらったときは 頭が痛くなるくらい乱暴で 顔もびしょぬれになったりもしてたけど きのうはずいぶん上手になっていた 顔のタオルはすべり落ちたけどね 甲田申由は 65分で髪をきれいに仕上げてくれて 「毎度ありがとうございます」って赤い頭を下げた 予定より短くなりすぎちゃったけど また伸びるから別にいいや 6ヵ月たって また髪ボサボサになってきたら 今度は本名を聞きに行こう 今年の12月にはどんな髪の色でどんな構想を練ってて たぶんもっと上手に洗ってくれるね それできっとまた 「髪は3ヶ月に一度はカットしたほうがいいですよ」って 笑いながら言ってくれる 店内改装の為 スリーエフの隣のタイラ書店で『ダ・ヴィンチ』を買ったら 添田さんがしおりをくれました 『広辞苑第5版』という黒いしおりです 添田さんはスヌーピーのこげ茶色のエプロンをかけています 私が添田さんが手を伸ばしかけてやめたルーペつきのしおりが 本当は欲しかったので 翌日は『文學界』でも買ってやろうと張り切って行ったところ タイラ書店はシャッターが下りていて 「店内改装の為しばらくの間御迷惑をおかけします」 という紙が貼ってありました 添田さんの不在を確かめるため 私はシャッターに耳をあててみましたが いつものローレライの鼻唄も聞こえず 13人もの通行人が私を見て行くのも気に入らず スリーエフでソントンのピーナッツクリームを買って帰りました 添田さんのエプロンは いつも右の長いちょうちょ結びです 十日後に貼紙はなくなって かわりにスヌーピーのプリクラが貼ってありましたが 期待に反して添田さんは写っていませんでした 黒いしおりで爪の垢をかき出すたびに私は スリーエフの壁越しに聞こえてくるようになった 電動ドリルの音を思い出し ピーナッツクリームの賞味期限はいつだったかしらと あせってしまうのです 複眼 先月9歳になったばかりの雌ライオンがいなくなった檻の前で 80過ぎの老人は 硬い音をたてる杖をついて コンクリートの床に残っている 水の流れた黒い染みから もう7分も目を離さない ときおり見物客に吠えては歩き回っていた 体長2メートルの彼女の名前を思い出せずにいるのかもしれない ベージュの帽子のつばに あきあかねがとまっていることにも 気がつかないで 砂利の上でどんどん液体に変わっていくソフトクリームを すみれぐみの青い名札をつけた女の子は見つづけている さっきまで「散歩道」を歌っていた母親が うしろで「ばか」と怒鳴りはじめるけれど ふたつ年上の兄が走っていった広いおりでは 灰色の象がバナナの皮をむいていて 父親のかたい手をかたく握ってうつむいたままでいるのは はぎとられて落ちる黄色の皮が 兄と母親の手のむこうがわに見えたからなのかもしれない 女の子はインド象とアフリカ象のちがいも知らないのに 生後3ヶ月のニホンザルが 杖の音といっしょに甲高く鳴くけれど ふり返ってみると バニラの匂いが充満しているだけで どうやら あきあかねは群れに戻ってしまったようだ 飛び回る無我夢中の影たちも もう薄くなりかけている バリケード 3日に一度 玄関の掃除をします 門のまわりをすみずみまで掃いて 砂を集めます 沈丁花の葉っぱは手でひろって 砂丘の完成です 竹ぼうきは 気味の悪い線ができるので よくありません ダイエーで売っていた680円の黒い毛のほうきが一番なのです ちりとりはポリエチレン製の黄色のがすてきです 雨が降ると掃除は延期です ダイヤモンドマンションの玄関で雨やどりしていたら 緑色のかっぱを着た管理人さんが掃除をはじめたので驚きました 管理人さんは砂丘をつくりません かっぱの帽子の下から 灰色の硬そうな髪がちょっとだけ見えていました 管理人さんは濡れた砂を花壇の横に寄せて 7分で完了です でも そのほうきの柄は短すぎるみたい それに 花壇の中にピンク色の花びらがたくさん散っている 玄関の掃除をしていたら ダイスケがやってきて 黒のコンバースで砂丘をつぶしてしまいました ダイスケは4ヶ月前に黄色のちりとりをくれたのですが 今度は熊手を買ってやると言っています 沈丁花はくさいと言って 春にはやってきません 熊手でひっかいたら 砂丘は崩れるんでしょう? 冬が来る前に沈丁花をあと5株植えたいの |
| よろしければ電動のこぎりを使ってください、と置いていったのだが、手入れの行き届いた銀色の歯は、私が所有しているのは不似合いだと思わせた。それも必要のない代物だと突き返してこなかったことを、今になって悔やんだ。 電気で動くのこぎりなんて、と私は思う。 私は押入の奥から段ボール箱を引きずり出し、金槌やペンチやスパナや箱全体に散らばった大小の鉄釘の中から両歯ののこぎりを手に取った。 薄い鋼の板の先に掌を当てて力を込めると、ぺおん、と妙に含みをもった高いとも低いともつかない音がする。 聞きつづけているうちに、隣室の住人がテレビの音量を上げたので、はっとした。 ぺおん、ともう一度だけゆっくりと鳴らした。 ところが襖にあいたミカンほどの穴に、音の余韻はことごとく吸い込まれてしまった。 強い北風のために希久子の指は冷えきっていた。 うちで待っておいでと言ったろう、と私が大袈裟に驚いた顔をしてみせたので、希久子は得意になったときの癖で口を閉じたままムムと笑った。その唇も紫に変わっている。 「ぬくい、ぬくい」と素頓狂な声をあげて希久子は私のポケットの中で、つないでいた小さな手を結んでは開き、「ゴゴクヤのあんまんの」と呟いてまた私の手を握った。 「希久子は肉まんよりあんまんが好きなの?」と私が昨日と同じ問いをすると、希久子は「肉はからいの」と同じように口を尖らせて答えた。 しかめっ面をして「大学は休みかい」と言っていた五穀屋の禿親父が「希久ちゃんにおまけだよ」と橙色の和菓子を希久子の手に載せた。 希久子はきゃあと高い声をあげて喜ぶ。 あんまんをつかんだ希久子の右手に力が入ってしまっていて、私が代わりに持ってやろうとすると、希久子は「きいちゃんの」と言って離さず、さらに強くつかんだので、あんがはみ出た。 希久子は得意げに柿の実を模した和菓子を私に見せた。 柿というにはあまりにも安っぽい色合いだと私には思えてならなかったが、希久子は心から喜んでいるのだった。それも、自分だけが親父からおまけをもらったことなどにではなく、玩具のような菓子の形状そのものを嬉しがっているのだろうと、私は希久子の手よりも温かい肉まんを掌に確かめつつぼんやりと思った。 歩きながら私たちは湯気の立つ中華まんを頬ばった。 後ろから冷たい強い風が、希久子のおかっぱの髪をからかっているように幾度も吹きつけた。 あんまんを食べ終えた希久子の掌に、柿の和菓子がちんまりと載っている。それで私は、糖分は欲しがるだけ与えてはいけないと叔母からいつも言われていることを思い出した。 希久子は私が見つめていることに気づいて「だめなの」と頭を振った。両手で包んで胸に抱き、頑なに「きいちゃんが食べるんだから」と言い張る。私が止めるのを不快だというように「ゴゴクヤのおまけなんだから」と駄々っ子のように頬を膨らませる。 私は、そんなにすぐに食べてしまっては柿がかわいそうだと、諭すように小声で言った。「生まれたばっかりなのに、食べてしまったらそれで死んじゃうんだよ。やりたいこともたくさんあるはずなのに、雪が降るのもまだ一度も見たことがないのに、希久子はかわいそうだと思わないかい」 「雪だるまも作ってないのに」と希久子が呟いて、私は少し上気した。 頬にあたる北風に早く熱が奪われるといいと私は願った。 「雪合戦は?」と私が言った。 希久子はうなずく。「春になったらつくし取りにも行くのに」 「つくしはどうやって増えるか知ってるかい?」 「卵?」 「つくしの頭から緑色の粉が出るだろう、それを飛ばして増えるんだ。それが種の代わりになるんだよ。たとえば、柿の実の中には大きな粒が入ってるだろう。それを土に埋めると芽が出て、木になって」 希久子は掌の中の和菓子をじっと見つめていた。 「じゃあ、これを埋めたら来年は柿がいっぱい食べられるんだね」 「来年は無理だよ。柿は芽が出たあと八年たってから実がなるというからね。だからいま種をまいても、食べられるのはずっとあとだ。希久子が二十歳になった頃だね」 私は笑って、希久子のこけしのような頭を撫でた。二十歳になった希久子と二十八歳の私がひとつの柿を分けあって食べる様子を、私は想像しようとした。しかし八年後の希久子の姿を、私はまったく思い描くことができなかった。 こみなみ公園の脇を通ったとき、希久子はつないでいた手を勢いよく振り切って、子供らが三、四人遊んでいるだけの公園へ駆け出していった。 まばらに咲き始めている山茶花の垣根のところで振り返って「お兄、早く」と飛び跳ねて手招きする。 「埋めて水やると、芽が出るの」講義をするように希久子は話しながらしゃがみ、枯枝で土を掘りはじめる。「次にふた葉が出るの。そのあとは本葉が出るの」 ジャングルジムの上の希久子よりも幼い少年らが私たちを見ていたのが気にかかったが、希久子に「お兄、怠けちゃだめ」と叱られて、私も枯枝を手にした。 枝が折れても希久子は作業の中断を許さず、ちびた鉛筆を最後まで使うように根気よく私たちは固い土を掘り下げた。ジャングルジムの少年たちには、墓を掘るように切羽つまっているように見えさえしたかもしれない。 和菓子を穴の底にそっと置き、上から軽く土をかぶせて表面をならしたとき、額から汗が一滴落ちた。 「今の水分で芽が出るな」と私が笑うと、「足りないよ」と希久子は言って、ありったけの唾液を土に垂らした。 そして私たちは折れた枯枝を周囲に挿して柵を作った。 「元気のある芽が出るといいね」と私は言った。 「甘い柿がいっぱいできますように」と希久子は目を閉じて合掌した。 長い祈りを終えると希久子は脇目もふらずに回旋塔へ走りつき、もどかしげに鉄の棒にぶらさがり「回して、お兄」とうわずった声で私を呼んだ。 回る速度が遅いと不平を言う甲高い声に動かされるように、私は鉄の棒をつかんで時計回りに無我夢中で送りつづけた。 頬っぺたを真っ赤にさせた希久子は「もっと速く」とはしゃいで笑い声をあげる。 お兄も乗って、と興奮したように希久子が叫んで、高速で回りつづけている鉄の檻に私は飛び乗った。 速度がいくらか緩み、希久子が「あれえ」と言う。それでも、降りようとする私を「きいちゃんがやる」と止め、不安定なかっこうで砂をまき散らし着地する。 ジャングルジムに登っていた少年らの一人が、速度を落とすまいと懸命に歯をくいしばり足をふんばって鉄の棒を操る希久子に恐る恐る近づいてくる。 「なに?」と回転する景色の合間から私が尋ねると、「二時だから帰っていらっしゃいってお母さんが捜してた」と少年は非難するような視線を私に向ける。 急に緩慢になった回旋塔から私は降り、まるで私が希久子のように、二時とは何かと希久子に問うた。 少年がすべり台のほうへ走るセーターの背中にすずかけの実がくっついているのがおかしいと希久子は笑い、「お母がうちで待ってるの?」と聞き返した。 私は叔母に黙って希久子を連れ出すということはしない。二時から用事があるのなら、あらかじめ教えてくれていてもよかっただろうに、と罪悪を咎められたような恥ずかしさで私は心のうちに叔母を責めた。 どぶ川のふちを通ってまで急いで帰ろうとする希久子を家まで送り、叔母に謝り、また私はこみなみ公園に戻った。 さきほどの少年たちは砂場に顔を寄せてしゃがみこみ、棒倒しに夢中になっていた。 そのうちに「さっきのやつだ」と小さな声がし、ほかの誰かが「頭のいかれたガキ連れ回してる男には気つけんだぞって吉田先生が言ってた」と仲間たちに知らせるのが聞こえた。 腹立ったわけではなかったが、私は右腕で回旋塔を思いきり回転させた。少年たちが押し黙る。 アパートの鉄階段を上ってもなお、そのやかましい音は消えなかった。希久子の乗った音はもう少し重く、しかし希久子と私の乗った音は捏造された記憶のように曖昧だった。 その夜、アパートの庭の貧弱な柿の木の熟しすぎた実のひとつを私はもぎ、例の場所に埋めた。指で触った部分がへこんでしまうほど柔らかな実は、一口かじってみるとやたらと渋く、翌日まで奥歯の根元がしびれていた。 晴れわたった青空に、高くクレーンが一本伸びていた。クレーンもショベルカーも停止してしんとしているのは、もう昼休みに入ったからなのだろう。日陰では作業員が三人、横になっている。ここ数日の雨続きのおかげで、この奇妙に穏やかな光景も久々に目にするものだった。 真上から射す太陽が、ヘルメットを通して頭にじわじわと熱を伝えていた。のぼせてしまいそうだった。 束の間の休憩を切りあげ私は再びエンジンをかけ、「今日は焼けるな」という班長の投げやりな口調を思い出しながらも、残っている一束を配ってしまってから戻ろうと決めた。 私のバイクの音を聞きつけて、希久子が門の前でぴょんぴょんと飛び跳ねて叫声をあげた。そのたびに、相変わらずきれいに切り揃えられているおかっぱが上下に撥ね、モスグリーンのスカートの裾がめくれてくすんだ膝頭が見え隠れし、左手につかんだぺんぺん草が幾本かアスファルトに落ちた。 叔母が玄関口に姿をあらわし「何事かと思ったわ」と大声を出さないよう希久子をたしなめる。私がはがきを三通手渡すと「いつもごくろうさんね」とそっけなく言って家へ引っ込んでしまった。 道に落ちたぺんぺん草を拾い集めて、希久子は私の空っぽの配達鞄にそっと収め、「こみなみ公園に行くの」と囁いた。 これから局に戻って弁当を食べなければならないと言うと、希久子は口を尖らせて私のヘルメットをぽんと叩き「熱い」と驚いて叫んだ。 怯えた視線が玄関に向いたので、私はバイクを降り、希久子の手を引いて走った。 すれちがう人たちが私たちを不思議そうに見る眼を、希久子はかたつむりの殻のようだと笑った。 公園の入口で希久子は汗ばんだ手を離し、肩で息をつきながら「お兄」と言った。 私は額から顎に流れる汗を腕で拭った。 山茶花の垣根の隣には、細い柿が生えている。芽が出てから希久子は毎日のように柿の生長を確かめに公園を訪れ、何らかの変化があるごとに息を切らせて私に知らせに来て「お兄」と声を弾ませ、そして葉が出た虫が出たと、私を引っ張って公園へ走るのだった。 「見て」と希久子は細い幹に近づいて振り返った。 光沢のあるつるりとした濃緑の葉がみごとに繁っていた。昨年までの貧相な印象はどこにもなく、弱い風が吹くだけで葉擦れが聞こえた。 希久子が背伸びをして葉をかき分ける。すると、筆ほどの細い枝にくっつくようにして咲いている花が現れた。黄緑色のがくの中央に、淡い黄色の紙が外側へめくれたような愛らしい小さな花弁がついていた。 がくが小さく花びらが壷の形をしているのは雄花だと私は希久子に教えた。 「六個あるの」と希久子はすぐに言った。そしてムムと笑った。 雌花の方は七つ咲いていたので、その数だけ実ができるはずだと言うと、希久子は「きいちゃんと、お兄と、お父と、お母と」と指を折り、うっとりと梢を見つめた。そして「甘い実ができますように」と六年前と同じように手を合わせて瞼を閉じる。 希久子は花の香りがバニラアイスに似ていると言った。 さながら幼児の散歩のように、つないだ手を前に後ろに振り、私たちは歩いて帰った。 ことわざより二年も早く実を結ぶのは希久子が一生懸命に世話をしたからだと私が褒めたとき、希久子は恥ずかしそうに「だって死んじゃうのはかわいそうだもん」と笑みを浮かべた。希久子の照れ笑いは、この十八年間で初めて見た表情だった。 つながった濃い影が短く、希久子はそれを小人だと喜んだ。 「小人はとんがり帽子をかぶってるのに」と、私のヘルメットの顎ひもを引っ張る。 希久子の頭頂部にふたつのつむじがあった。もつれている髪を手でついてやると、汗の匂いが立った。 造成地ではショベルカーがすでに土をすくい出し、ダンプトラックの荷台に移す作業を再開していた。 木が高くなって実に手が届かなかったらクレーンを使えばいいんだねと希久子は言った。 九月に入ってすぐ、母親が訪ねてきた。霧雨が朝から降りつづいている日曜日だった。 手土産の梨をむいて「甘いから」とすすめ、窓の外の青い実のついた柿の木に目をやって「ずいぶん伸びたのねえ」と、母親はほうと息をつく。 一瞬、自分が中学生に戻ったように感じられ、私は「何年も見てなかったからだろ」と答えた。 案の定、母親は「来年はもう二十七になるんだしね」と返してきた。 私は梨の皿のふちに留まった目の赤いショウジョウバエを手で追い払い、田舎から送ってもらったというそのみずみずしい果物を食べた。 「そろそろ考えたらどうかしら」と母親が身を乗り出してきたので、私は「今のところは必要がない」と先回りして答えた。 話の腰を折られて母親は途方に暮れたように「ちゃんと仕事に就いてもいるし……」と消え入るように呟いたが、私は取り合わなかった。 ちょうど電灯の紐に留まったショウジョウバエを母親が叩き落としたとき、表の鉄階段を駆け上がってくる大きな足音がした。私はそれが希久子だとすぐに判ったが、母親は「うるさいわねえ」と眉をひそめた。その瞬間、母親が叔母にそっくりだということに気づいて、私は愕然とした。 扉を開けて、希久子が黄色いカッパを脱ぐのを手伝ってやっていると母親は「希久ちゃんだったの」と笑顔になった。 「梨」と希久子が指さしたので「あとで希久ちゃんのおうちにも持って行こうと思ってたのよ」と母親は「希久ちゃんに持って行ってもらおうかしら」と部屋の隅を示す。 希久子は「やったあ」と、その紙袋を持ち上げる。 「重いわよ」と母親が注意を促したとたんに、梨がひとつ毛羽だった畳にどすんと落ちた。希久子が拾おうとして屈んだので、梨は次々と袋からこぼれ落ちた。 よろけた希久子が押入の襖に勢いよくぶつかった。 「希久ちゃん」と母親が立ちあがった。「大丈夫かしら」という声の合間にも、六畳が梨だらけになりつつあった。さすがは水分の詰まった実だけあって重量感のある音が耳に残った。 母親が希久子の手を取って立たせ、血のにじんだ肘に「ばんそうこうを貼りましょう」と言っていた。 希久子を家まで送り、母親が叔母に挨拶をしている間に、私はひとりでこみなみ公園へ行ってみた。 木には青い柿が七個、枝にしがみつくように実っていた。 希久子は柿泥棒がやって来るのではないかと心配している。もうしばらくして熟した柿を食べたとき、希久子はその渋さを何と言うだろうかと私は想像した。 「甘い実がなりますように」と私は真似をしてみて、急にばかばかしくなった。渋柿を埋めたのだから、しょせんは渋柿しか実りはしないのだと、分かりきっていることを私はくりかえし考えていた。 襖の穴のふちに私は指をそっと這わせて、ゆっくりと一周させた。 梨が畳に落ちる音をまた思い出し、合掌して祈る十二歳と十八歳の希久子を思った。 母親が戻ってきて、先に帰ってしまうとは失礼ではないかと私を非難した。それでもにこにことしているので、何かあったのかと私は尋ねた。 母親は「私も齢とるはずよねえ」と日本茶をすすった。皿には叔母からもらったという和菓子が四つばかり載っている。 「姪がもう結婚だなんていうんだから」 希久子のことかと訊くと、母親はほかに誰がいるのと叱った。そして、希久子を十分に世話してくれるちからをもった男性との話が進んでいるらしいと話した。どんな人なのかはよく聞いてこなかったんだけど、希久ちゃんとはもう何度も会ったりして、けっこう気が合うみたいなんですって。 母親は「いいニュースがあると家に帰りやすいわ」と言い「でもやっぱり披露宴はやらないそうよ」と一人で頷いて熱い茶を注ぎ足した。 皿の和菓子を母親は「きれいな色だから食べるのがもったいないわ」と言いつつも、たて続けにふたつもぺろりと食べた。五穀屋の菓子だろうと私が言うと、母親は「お土産に買って帰ろうかしら」と呟いた。 秋になると柿をかたどった菓子が出ることを言いかけると、母親は私の言葉を遮り、「その柿のお菓子も用意してくれていたんだけど、希久ちゃんに食べられちゃったんですって」と苦笑した。 母親は喋りつづける。「結婚っていっても、希久ちゃんは家事だってできないし、もし子供産んだとしても育てられないかもわからないよ。体だって心配だし、それにさ、希久ちゃんと同じような子供ができるかも……」 私が黙っているのを、関心がないのだと受け取ったらしく、母親はわざとらしく音を立てて茶を飲んだ。 悲しい気分だった。 縁談が本決まりになって忙しくなったのか、あるいはむやみに遊びに出ることを禁じられてるのかもしれないと、私は希久子が会いにやって来ない理由をいろいろと推察した。 配達で回っても、門で待つ希久子の姿はなく、一度だけ叔母と会ったが「いつもごくろうさんね」とすぐに扉を閉められてしまった。 母親は相も変わらず「そろそろどうかしら」としばしば連絡をよこしてきている。私はひとつひとつを断り、まだ必要性を感じないことを説明した。 休日にはひとりで公園へ行った。 すずかけの実がつき、山茶花の蕾が目立つようになり、初めての柿の実は橙色になりかけている。 子供らから柿を守るために、私は一日じゅうベンチに座って木を見張っていた。何時間も公園でぼんやりしている私を子供らは「けんかして追い出されたお父さんだよ」と噂し、時には人さらいだとも言っていた。 誰もいないときには、回旋塔を回してみることもあった。すると決まって鉄の檻は六年前と変わらない大きな音を立て、私は「お兄、もっと速く」とはしゃぐ十二歳の希久子が乗っていればと思ってしまう。 一昨年、手をつなぐのはいやだと希久子が頑なに拒んだ時期があった。理由を問いただしてみると、どうやら叔母が禁じたことのようだった。美しく成長した指に私の節くれだったまめだらけの手で触れるのは確かに気の引けることではあったが、私は聞き入れずに希久子の手首をつかむようにして歩いた。そのうちに再び手をつなぐようになったので、私は希久子は母親をひとつ越えたのだと思ったのだが、それは重大な誤りだったのかもしれない。 「芽が出た」と起きぬけの私を公園に引っ張っていった希久子は、山茶花のそばにしゃがみこんで、日が高くなるまで飽きもせずにずっと眺めていたのだった。希久子がアパートの扉を叩きながら「お兄、芽が」とくりかえし叫んだ朝、私は希久子の夢を見ていたのではなかったか。 私のことや柿のことを、希久子はもうすっかり忘れているのかもしれなかった。 灰色の作業服に身を包んだ初老の男が近づいてきて隣に腰を下ろした。 「空が高くなってきましたね」と男が言い出したので、私はもう二十回以上は同じことをしただろうと思いながらも、上空を仰いだ。つい五分前に見上げたときと、いわし雲の形はほとんど変わっていなかった。 「山茶花もプラタナスも、今がいちばん美しい時期ですね」と男はひとり頷き、「住宅街の児童公園に柿とは珍しい」と顎ひげを撫でた。 話を聞いていると、男は市から委嘱されている公園の整備業者のようだった。 「子供たちが遊びに来ない公園ってのは寂しいもんだよね」と男は乾いた笑い声を出し、私が返事をしないことなど気にも留めない様子で続けた。「あたし今日は下見に来たんですよ。この時に子供らが賑やかにやってると、それも却って悲しい気分なんだけどね。おじさん何してるのってよく話しかけられるんですよ。おじさんは公園を点検してるんだよって言っても、子供は何で点検してるのってしつこく訊いてくるんだ。でもあたしは公園をつぶすためだなんて答えられない。そうでしょう? 国有地か何かになって草っぱらになるだけなんて場合は特にね。マンションを建てるんだよって言うほうがまだマシだ」 青々としたすすきの茂った原っぱを風が渡り、葉の流れる爽やかな音が聞こえそうだった。そして今頃の季節には一面をふわふわの穂が覆いつくす。 「何かが建つんですか」と私は尋ねた。 男はすばやく周りを見回してから「取り込まれたんだ。建売住宅が4軒ほど建つね」と低く言い「あの回旋塔はかなり古そうだね」と、メモ用紙に『耐久性限界』と乱雑に書きつけた。 翌週の休日、短く刈った不自然なほど黒い髪を撫でつけて、自治会長は「困ったね」と苦笑いした。 「困ってるのは私のほうですよ」と声を強くし、私ははっとして「個人的なことで申し訳ないと思いますが」と少し気を落ちつけてつけ加えた。 「要するにさあ」と自治会長は掛け時計に目をやりながらタバコを押しつぶした。「柿の木なんでしょう?」 そんな理由では市に上申できないし、第一もう本決まりなのだから今から取りやめになったりでもしたらたくさんの人が迷惑を被ることになるのだと言って、自治会長はソファから腰を上げ、「残念ですけど、こみなみ公園を残すのは今となってはもう不可能ですよ。でも僕だって壊せ燃せと言ってるわけではありませんよ。僕も庭いじりが好きですから、木が切られるのは不愉快だ。木をどうしても守りたいんだったら、工事の前に別の場所に植え替えるしかないんでしょうねえ。あ、もしよかったら用具はお貸ししますよ。あの柿を掘り出すのにちょうどよさそうなスコップもありますし。柄がちょうどいい太さで……」 「必要ありません」と私は母親に言うようにきっぱりと断った。 自治会長は私の態度が一変したことを当然だとでもいうように満足げに頷いて「それなら電動のこぎりでも持って行きますか」と笑い、五穀屋の菓子の礼を言った。 十六夜も、厚い雲に覆われて月を見ることはできなかった。鋼に反射するのは街灯の明かりだけだった。それでも、調子に乗った子供のように私は両歯のこぎりをぺおんと幾度も鳴らして歩いた。これからやろうとしていることは生命を絶つことなのだと知っているのに、私は自分でも驚くほどに上機嫌だった。 柿も山茶花もすずかけも、風に吹かれた葉から微かに音をたてていた。黒く見える柿の葉の表面が、ベンチ脇の水銀灯に照らされてつやつやと光っていた。実はよい色に熟している。数えてみるとひとつ足りなかった。どこかの子供にもぎ取られてしまったのかもしれないと私は想像した。六年前に埋めた柿のひどい渋味を思い出して、勝ち誇った気持ちで私は悔しがる子供を思い描いた。 いっそう強い風にあおられて公園内がざわめき、すずかけの実がいくつかぽとりと音をたてて落ちた。 幹の根元は、両手の親指と人差し指で作った輪よりも細かった。 ひと挽きすると、樹皮がはがれ落ちた。 次は粉のような木屑があふれ出た。そのあとはただひたすら挽いた。額から顎に伝った汗が落ち、土にしみ込んでいった。挽きつづける音が風の音をかき消した。 風で舞い上がった木屑を吸い込んで、私はむせた。鼻や喉の粘膜に粉が張りつき痛んだ。知らぬうちに眼が潤み、私は腹立たしくなって思いきり瞼をこすった。すると眼にも木屑が入って、さらに涙が溜まった。 作業を続けようとしたとき、しまったと思った。直後、鋭い痛みとともに左手の甲に赤い破線が滲み始めた。 四分の三ほど切ったあたりで、木は蕾の膨らんだ山茶花の垣根を潰すように倒れた。残っていた四分の一の幹を引き裂く音に、私は悲しさもほとんど感じなかった。ついにやった、とさらに上気したくらいだ。 今ここに斜めに横たわっているものが、六年前の夜に密かに埋めたものの姿なのかと、私は信じがたい気持ちで眺めた。 芽が出たと希久子が踊り、赤いジョウロで水をやった木を私が切り倒した。バニラアイスの匂いだと希久子がはしゃいだ春が、ずいぶんと昔のことのようにも思えた。 肘の傷はもう治っただろうかと私はまたいつもの考えにとりつかれる。この傍らに今、はにかむ希久子がいるのだったら、私は小さなつむじのふたつあるおかっぱ頭を撫で、襖より強いと言って肘をさすり、「回して、お兄」とせがむのを「齢を考えなさい」とたしなめ、華奢な手を恐る恐る握って、あんまんを買いに行こうと言い出すしかなかっただろうと思った。 しかし希久子は、この山茶花に覆いかぶさっている柿をかわいそうだと言うに違いなかった。そして、ひどいことをしたと私をなじり、泣くだろう。 それでも私は左手の傷を差し出して、両歯のこぎりで助かったと大袈裟に言ってみせ、電動のこぎりを見たがる希久子に「じゃあ、うちにおいで」とでも言うのだろう。 まんべんなく橙色に変わった六個の実を、私は残らず摘んだ。手の中にすっぽりと収まる小ぶりの果実は、葉と同じように光沢があり、つるつるとしていた。 すがすがしい気持ちで私は回旋塔に乗った。やかましい鉄の音があたり一面に反響する。徐々に速度を上げて回転する景色を眺めているうちに、そんなはずはないのに、ここは希久子が「お兄」と呼んだ公園ではないような気がしてきた。 私は飛び降り、並べた実のひとつを、まだ回りつづけている檻に投げつけた。鈍い音がし、ぱっくりと割れて焦茶色の平たい種子を覗かせた断片が足元に転がってきた。なぜ戻ってくるのかと、私はまた腹立たしくなった。 それを拾い上げ、口に入れてみると、砂の粒がじゃりじゃりと鳴った。だが、いくら待っても渋味はやってこなかった。私は回旋塔のそばに落ちているもう一片の柿を食べた。甘かった。 ベンチの横のくずかごに、木をまるごと突っ込んだ。そこまで引っ張って行くのには息切れがしたが、まるでくずかごを突き破って生えてきたかのような格好になり、私は思わず笑ってしまった。これなら希久子も泣くことはないかもしれないと思った。 一部が無残に引きちぎられた切株は痛々しかった。直径は十センチにも満たないだろう。送るべき先を失いながらも、地中の根はまだ水を吸い上げつづけているのだろうと思った。いずれまた芽吹くために、何も知らずに着々と養分を貯え込んでいるのだろう。 本来ならこの場所に根づくはずのなかった木だったと、私は六年ものあいだ思っていた。元はといえば私の都合のためにもがれて埋められた柿にすぎなかった。あのような濃厚な甘みをもった果実など、私は欲していなかった。私があの一個の渋柿に求めたのは発芽、ただそれだけだった。 それを思い出させるおがくずと、はげた樹皮を散らして地面から突き出ている切株が目障りだった。視線を外そうと意識すればするほど、細い切株は大きく感じられた。 クレーンもショベルカーも、いつの間にか姿を消し、今はフェンスの向こうの雑草一本生えていない更地が、ただ雨を吸い込んでいるだけだった。 配達鞄にかぶせた防水シートに雨粒が叩きつける音を、朝からずっと聞いている。靴の中までがじっとりと濡れて、冷えきっていた。局に戻って、かじかんだ手で熱い缶コーヒーを包む安らぎを一方で思いながらも、私は希久子のことを考えつづけた。 今日もやはり希久子は門のところに姿を見せなかった。 情けないと思いつつ、わずかな希望を期待して、私はわざと緩慢な動作で局に戻る準備をしていたのだった。エンジンの不調を装い、何度もバイクに乗ったり降りたりもした。諦めて出発しようとしたとき、ちょうど買い物から帰宅した叔母に出くわした。 「いつもごくろうさんね」と叔母が会釈するのを待って、私はすかさず「希久子ちゃんは元気ですか」と訊いた。 叔母は眉をひそめた。私の唐突な質問を不愉快に思ったのだろうと想像したが、かまうものかと私は「しばらく会ってませんが」とつけ足した。 叔母はしかめっ面のまま、希久子は病院にいると言った。「お母さんから聞いてないの? 再発かもしれないって」 叔母は明らかに不機嫌そうにそう言い放って、郵便受けも覗かずに家へ入った。 一日じゅう制服のポケットに入れっぱなしにしていたので、封筒はよれて、しわだらけになってしまっていたが、カッパを着ていたおかげで濡れてはいなかった。丁寧にしわを伸ばしてから、ロッカーの扉を借りて『久住希久子様』と書いた。耳に馴れない新姓は、文字にしても妙に居心地が悪い。 隣で、班長が濃緑色のネクタイをゆるめながら「何だ、その封筒は」と大仰に嘆いた。「女に送るんだったらビシッと黒か白に決まってんだろうが。そんな女々しい色じゃあ、相手にしてもらえねえぞ」 つられて私も笑い、班長がぬるい缶コーヒーをくれたのでそれを飲み、明日も肌寒いのだろうかと少し話した。 日はもう落ちていた。急な傾斜の坂をのろのろと登りながら、すれ違う市営バスの乗客に叔母がいはしまいかと顔を隠すように傘をさしている自分が滑稽に思えた。 歩道にはすずかけの実が、足の踏み場もないくらいにびっしりと落ちていた。それで、一歩ごとに殻の割れる音がするのだった。 私が見舞いに来るのを知っていた、と希久子は言った。 なぜかと私が問うと、希久子は「秘密だよ」とムムと笑う。おおかた、坂道を登ってくる私を窓から見つけていたか、それでなければ叔母が何かを話したのかもしれないと私は見当をつけた。「郵便です」とドアを叩いた自分を思い出すと恥ずかしくなった。 希久子は宛名を声に出して読みあげ、「お兄、名字が間違ってるよ」と言った。 「それでいいんだよ」と、枕元に積み重ねられたグリム童話集から目を離して私は答え、帰りがけに押してきた消印を指差して、今日の日付が記されていることを教えた。 希久子は手紙を開封せずに、大人びた仕種で私に椅子をすすめた。 私は、見舞いの品がくしゃくしゃの手紙一通しかないことを詫びた。 すると「花束なんてすぐにしおれちゃうからいらない」と希久子はすねたように言った。その視線を追うと、窓際に空っぽの花瓶があった。花は生けられていなかったが、茶色く変色したカスミソウの花がいくつか散らばっていた。 「くんちゃんが持ってきた花はしおれちゃったから、お母が捨てたの」 くんちゃん、と私は呟いた。それが希久子の婚約者の愛称であることはすぐに想像がついた。 私は希久子に婚約について何かを語ってもらいたいと思っていた。とりわけ、以前のように私たちが公園で一緒に遊んだり、手をつないで歩くことができなくなったことについて希久子がどのように感じているのかを知りたかった。 廊下ではワゴンのゴム車輪がリノリウムとこすれる音がしはじめ、煮物の甘辛い匂いが病室にまで流れ込んできた。 耳元で母親が低い声で囁いているような気がした。結婚っていっても希久ちゃんは家事だってできないし。 「今度くんちゃんに会わせてくれる?」 「やだよう」 「どうして?」 「お兄こそ、なんでくんちゃんに会いたいって言うの?」 希久子は布団カバーを力いっぱいにつかみ、今にもべそをかきそうな震えた声で言った。柿の木が切り倒されたことを知ったらこのように目を潤ませるのだろうと思いながら、私は希久子の涙目を眺めた。そして「死んじゃうのはかわいそう」と希久子は切株に手を触れる。 そのとき私は、希久子にとって久住氏は、単なる仲よしさんの一人にすぎないのではないかと思った。私と同じような、楽しいことをたくさん持ってきてくれる「お兄」がひとり増えたのだという程度にしか、希 久子は久住氏を見ていないのではないかと。 「昨日、柿を収穫したんだよ」希久子の固く結ばれた滑らかな拳に、私は冷えきったままの右手を重ねた。徐々に力が緩んでいくのが伝わってきた。 「七個ぜんぶ食べちゃったの?」 「あと五個も残ってるよ。つやつやして、きれいな橙色をしてる」 「きいちゃんも食べたいよう」 「そうだね。柿もきっと一生懸命に育ててくれた希久子に食べてもらいたいと思ってるだろうね」 私がそう言うと、希久子はこそばゆそうにはにかんだ。 ワゴンを押してきた看護婦が「面会時間はとっくに終了してますよ」と迷惑そうに私を見た。 「お兄なの」と希久子は私をかばう。そして「郵便屋さんなの」と橙色のしわくちゃの封筒を差し出す。 希久子とそう齢の離れていないやせぎすの看護婦は、黄ばんだトレイを希久子の前に置きながら「名字が違うんじゃないの」とつまらなさそうに言った。 お兄が間違えてくんちゃんの名前を書いちゃったの、と希久子は「く・ず・み」と言う。「き・く・こ。変なのお」 その晩は瞼を閉じると、すずかけの実がぽとりと落ちて踏まれる妙に鮮やかな音がしつこく蘇るので、なかなか寝つけなかった。 ときどき、叔母の無愛想な声や、やかましい回旋塔のうなりが混ざり、生きた幹の裂ける音と、梨が転がる音が我先にと加わった。そして「お兄」と高い声がするかと思うと、決まって聞いたこともない電動のこぎりの悪寒を催させる耳障りな音がそれをかき消すのだった。 翌朝は頭痛がひどく、喉が腫れ、鼻がつまって呼吸もままならなかった。ぞくぞくと寒気がし、めまいを耐えながら体温を計ってみると九度近くまであった。 電話口に出た班長は「そういや、顔色悪かったもんなあ」と言い「バファリン飲んでひとり寂しく寝とけ」と、頭に響く笑い声をあげた。 希久子は五つの柿を楽しみに待っているだろうと思った。それから、手紙をもう読んだろうかと考えた。柿を切り倒したあと、私は明け方までかかって便箋に向かっていたのだった。しばらく会っていないことが寂しいと書き、こみなみ公園が潰される話を聞いたことを書いた。『でも、下見に来てたおじいさんも悲しそうだったんだよ』 布団の中で私は、希久子に風邪をうつしてしまってはいまいかと心配になった。そして希久子の病気とは一体何なのかと当てもなく考えた。しかし皆目見当がつかず、浅い眠りから醒めては、襖の穴に目をやった。 母親の置いていった梨の腐臭が日ごとに部屋に満ちてきていた。ショウジョウバエの羽音が耳元で聞こえる。うとうとしていると口の端や目尻に留まることもあった。 夜に、母親から電話があった。「番号を間違えたのかと思ったわ」としゃがれ声に驚いたので、熱が高いことを話した。母親は温かいレモネードに蜂蜜を入れて飲むとたちまち効くのだと妙に得意になって説明し、レモンも蜂蜜もないと私が答えると、「とにかく胃に何か入れなさい」と言った。そして深い息の音が聞こえた。 私が用件を促すと、母親は「お見舞いに行ったって聞いたから」と要領を得ない言葉を返してきた。 横道にそれてばかりの話をまとめると、どうやら、もう見舞いには行くなということを母親は言いたがっているようだった。「向こうのかたのお気持ちもね」と言葉を濁してはいたが。そして、近いうちに希久子が転院することを聞いたと言った。久住氏の実家に程近い大きな総合病院だと母親は話した。電話口の母親の声は動揺しているように感じられ、もしかすると叔母を通じてではなく、久住氏から直に諌められたのかもしれないと私は思った。しかし母親は見事にはぐらかした。 おおかた、希久子が久住氏の前で「今日、お兄がねえ」とはしゃいだのだろうと私は想像した。事によると手紙も取り上げられてしまったかもしれない。 だが、疎外されたような不愉快な気持ちはすぐに消えた。そしてじわじわと安堵感がやってくるのがわかった。もちろん、理不尽なことに対する反発もありはした。それでも私は、久住氏がきわめて人間的な感情をもった男でありそうだという予感に、嬉しさをおぼえたのだった。叔母の人を見る目もそう枯れてはいないようだと見直しもした。私とは正反対の男を叔母は連れてきたのだった。 窓を開けて、柿にまで群がっていたショウジョウバエを追い払うと、冷たい夜風が吹き込み、ほてった体に心地よかった。 今夜も月は出ていなかった。紅葉しはじめた柿の葉は夜目に黒い影となりそよいでいる。近頃はヒヨドリが実をつつきにやってくることもあった。実のいくつかは地面に落ちて、種子をあらわにして潰れていた。 その枝も葉も、つけた実までもが、私が埋め私が切った柿のものとそっくりだった。 私は身を乗り出して、ちょうどよく熟した実をひとつもぎ取った。 よく見れば見るほど、公園で採った柿と見分けがつかなくなった。どちらも丸々とし、明るい橙色の表皮はつやをもち、厚く堅い淡緑色のへたがついていた。あまりによく似ていた。同一の枝から摘んだと言ってもおかしくないほどだ。 しかし、やはりこの実には強い渋味があった。奥歯の根元がしびれ、私はたまらなくなり吐き出した。すると、どうしようもなくおかしさがこみあげてきた。 大雪の降った十二月二十七日に希久子からはがきが届いた。『明けましておめでとうございます』という鉛筆書きの不揃いな文字は、紙がへこむほど強く書かれていた。『きょ年はお手紙をどうもありがとう』と希久子は書いていた。『公園がなくなるとあそぶばしょがないのでいやだと思います。でもまたあたらしい公えんを作るってくんちゃんがいってたよ』そしていびつな鳥籠のような回旋塔と雪だるまの絵が描かれ、今年もよろしく、と書き添えられていた。 極端な右肩上がりの細い文字で『久住希久子』とだけ記されていた。住所はなかった。 表側に浮き出た文字や、今にもはがれそうな五十円切手を、襖の穴をそうするように私は中指の腹でそっと撫でた。 次に届いたはがきは久住氏からだった。新芽の吹いた枝が窓の向こうに誇らしげに突き出している暖かい日だった。 例の右上に引っ張られた、思わず笑みがもれるほどユーモラスな文字で久住氏は、妻が他界したこと、葬儀はごく内輪の者だけで執り行ったこと、そしてあおば霊園の住所を書きつらねていた。 こみなみ公園の三つの出入口にはロープが張られ、『関係者以外立入禁止』のプレートがぶら下がって揺れていた。遊具もすべてロープに巻かれ、『使用禁止』の紙が貼られていた。もちろん回旋塔も、動かないようにがんじがらめに縛りつけられていた。 山茶花はもう一株も残っていず、枝は無造作に隅の方に積み上げられていた。ちょうど作業員たちは三人一組になってすずかけに取りかかろうとしているところだった。幹をどちら側に倒すのかを話し合っているのだと男は教えてくれた。 子供たちがフェンスの金網にしがみついていた。男は顎ひげを撫でながら、その小さな背中に目をやり、「あの子たちね、今朝あたしたちがブランコやらすべり台やらにロープ張ってたときに来てさ、この公園がどんなにいい公園かって説明しはじめたんだよね。どこの公園でもあたしたちにとっちゃよくあることだから、正直またかよって思うんだけどさ、そういうときの子供らときたら、えらく必死なんだよね。わざとらしく泣きわめいたりはしないんだ。その代わり、あたしの話を聞いたあとも黙ったままずっと様子を見てる。そのうち、あたしたちまでもが何だか悲しい気分になってきちゃうんだよね。あいつらの気持ちがうつるんだよ。インフルエンザだ」 確かに、子供たちは押し黙ったまま作業の様子を見つめているのだった。彼らが私くらいの年齢になったとき、この光景はどんな色合いになって思い出されるのだろうかと私は思った。回旋塔のやかましい音や、すずかけの甘い芳香、そしてこのフェンス越しの光景も、彼らの記憶に留まりつづけるだろうと思った。 縛られた回旋塔が気の毒に思え、私は錆びついた音を思い出そうとした。しかし、電動のこぎりの回転音が私の思考を遮った。 子供たちがさらに高くよじ登って、ジェイソンの話をしはじめた。 影を歪めたかと思うと、すずかけはあっという間に倒れた。重たげな響きが地面を通して靴の裏に伝わってきた。この震えを希久子なら何と言うだろうかと思った。私はこの感触をひとりきりで封じ込めなければならないのだった。 あたりは静かだった。生温かい空気がよどみ、ときおり遠くからは微かに雷鳴が聞こえる。見ると、ねずみ色の厚い雲が低く垂れこめている。 まだ新しいカスミソウが生けられていたので、私は道すがら摘んできたぺんぺん草を横から押し込んで一緒に供えた。 線香の先の橙色に浮きあがった火から、細い白煙がたなびいている。 あまりに静寂が強かった。 甘い実ができたんだよ、と私は思った。五穀屋のあんまんよりもずっと甘いんだ。 やがて、大粒の雨がカスミソウを揺らし、墓石を叩く雨音があちこちで聞こえはじめた。 掌中の種子を私はばらまいた。いくつかは墓石に当たって跳ね返り、いくつかはスギナの奥へ転がっていった。焦茶色の小石のように、それらは周囲の景色に溶けこんで、すぐに見えなくなった。 六年なんてすぐに過ぎるからね、と私は思う。 しかし左手の甲のむずがゆいのがそれまでに消えるとは、とても思えなかった。 |
![]()
一代目日記 | 二代目日記 | 猫たち | 食べもの | 書庫 | 植物 | 写真集 | リンク | 掲示板 | 自己紹介
十穀おむすびといっしょに。
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
